第八話 青年インカ(16)
一方、クスコの牢を脱出して以来、追っ手の前からも、そして、インカの民の前からさえも、忽然と姿を消していたトゥパク・アマルは、果たして、この頃、何処にいたのであろうか―――。
彼は、この時、インカ軍本隊の一部と共にインカの天空都市マチュピチュ(Machu Picchu)にいた。
厳重な地下牢を破り、秘密の地下道を使って妻子と共に敵の手中から逃れた彼は、未だ、スペイン軍から執拗な追跡を受けていた。
故に、この山岳の秘密都市は、敵軍が近づけば即座に察知し得る地の利を有しており、追っ手から身を隠すには最適な場所である。
マチュピチュの総面積は約13キロ平方メートル、標高は2,057メートル 、古(いにしえ)の最盛期には1万〜2万人の人口が暮らしたとも言われる。
インカを巨大な帝国へと導いた第9代皇帝パチャクティ(Pachacuti)によってインカの王族や貴族のための離宮として建設されたが、スペイン侵略後は、その自然の要害を生かして、インカの末裔たちが反乱の拠点としてきた場所でもある(註:マチュピチュの成立過程、及び、放棄等の経緯については、未だ確定的な定説が無いため、物語中の文章は、現時点での有力な見解に基づいて記載。なお、近年では、インカ帝国最後の都は、「エスピリトゥパンパ(聖なる平原)」と呼ばれる地で、マチュピチュではないとする説も有力である)。
トゥパク・アマル(註:この物語の主人公トゥパク・アマルは、正確には、トゥパク・アマル2世である)がその名を継ぐトゥパク・アマル1世も、かつて秘密都市を拠点にスペイン軍との壮絶な戦いに挑んだ――そのトゥパク・アマル1世も、最終的には白人の手に落ちて処刑されたが、処刑台を前にしながらの彼の毅然たる沈着な態度は、今もインカの末裔たちの心に深く刻まれている。
マチュピチュは、猛然と流れるウルバンバ川に囲まれた断崖絶壁の頂上斜面にあり、山麓からは、決して、その姿を確認できない。
インカ特有の精緻な石積建築の城壁に堅固に囲まれ、太陽神殿、宮殿、祭壇、住居等が階段式に並び、周囲に広がる長大な段々畑(アンデネス)は優れた灌漑設備を有して豊富な食料生産が可能であり、まさに要塞空中都市と呼ぶに相応しい立地と機能を有する。
しかしながら、インカ帝国侵略後200年以上も経た現在、トゥパク・アマルの眼下に広がるマチュピチュは、すっかり廃墟の遺跡と化していた。
ところで、マチュピチュは、厳しい自然に囲まれた山の頂(いただき)にありながらも、ここから多数のインカ道が旧都クスコをはじめとして国中に伸びており、絶海の孤島のごとくの当地にありながらも、国中の情報を仕入れ、また、指令を放つにも非常に優れた機能を有する場所でもあった。
トゥパク・アマルは、いずれ遠からず、マチュピチュから下界に降りて再び反乱を率いるその日に備え、妻ミカエラ、長男イポーリト、末子フェルナンド、そして、護衛の軍団と共に、一時的に、この地に腰を落ち着けていた。
今、彼は、ワイナピチュの頂に立ち、眼下のマチュピチュを見下ろしている。
ワイナピチュは、マチュピチュの背後に聳(そび)える山で、急峻な獣道を登っていくと、山頂まで上りつくことができる。
その山頂には、かつて歴代のインカ皇帝たちが座した一枚岩の堅固な玉座があるが、そこからは、眼下に広がるマチュピチュの美しい街並みの全容を、遥々と俯瞰することができるのだ。

往年のインカ帝国の栄華を偲んでいるのか、あるいは、今後の反乱の展開を見据えているのか、黙って眼下の遺跡を見つめるトゥパク・アマルの精悍な横顔は、清冽な蒼天を背景にくっきりと映えている。
逞しく引き締まった長身に纏う黒マントと漆黒の長髪が、冬の冷風の中に舞っている。
ワイナピチュの頂に浮き上がる凛然たるその姿は、黄金色の陽光を受けて高貴で霊妙な覇光を放ち、まるで天空から舞い降りた太陽神の化身のようにさえ見える。
彼の元で再び護衛の任についているビルカパサは、少し離れた場所から感極まる思いで、そんな主(あるじ)の姿を見つめていた。
(トゥパク・アマル様……!
また、こうして、あなた様にお仕えできる日が来ようとは…!)
かつて、己の不始末でトゥパク・アマルが囚われてしまったと自らを呪い責め苛(さいな)んできたビルカパサの目頭は、トゥパク・アマルを目の前にする度、熱くなった。
そして、今度こそ、二度と、トゥパク・アマルをあのような苦境に追い込むまいと、己の胸の内で幾度と無く堅く誓いを立てていた。
ビルカパサの視線の先で、今、遥かなる聖都を、切れ長の目を伏せるようにして見下ろす主の横顔には、深い憂愁が宿って見える。
このマチュピチュでは、神殿や宮殿跡のみならず、かつてのインカの庶民たちの居住区も、ほぼ完全な形で残されている。
静寂な佇まいを今も見せているそれらの町並みに、ゆるやかな視線を注ぎ続けるトゥパク・アマルの胸の内は、静かに熱く込み上げる。
インカ帝国の首都であったクスコをはじめ、かつてのインカの町々では、侵略後、一般庶民の住居はスペイン人たちによって悉(ことごと)く破壊されてしまっていた。
しかし、眼下に広がる天空の秘都マチュピチュは、最後までスペイン軍の侵入を断固として許さなかったが故に、他所では破壊し尽くされた庶民たちの居住区も――今は、廃墟となった石組みの壁のみとはいえ――当時のままに残されているのである。
インカ帝国時代には、それら石組みの建造物は藁で屋根が葺(ふ)かれ、神殿や王宮は豊かな黄金で飾られ、長大で繊細に築かれた無数の段々畑には、ジャガイモ、トウモロコシ、ユカ、キノア、コカの葉など200種類以上の作物がたわわに実っていた。
だが、それほどに豊饒で堅固であったこの天空都市も、生き延びているインカの王族や兵を抹殺しようと執念の炎を滾(たぎ)らせて迫り来る執拗なスペイン軍の侵攻を食い止めるために、最終的には、やむなく当時のインカ皇帝や民たち自身の手によって焼き払われてしまったのである。
それは、トゥパク・アマルが生まれるよりもずっと昔の、彼の何世代も前の祖先たちの時代のことであるが……。
ひっそりと静まり返った廃墟と化したマチュピチュだが、それでも、今は、その一角に張られた彼の率いるインカ軍の天幕から、吹き上げる風に乗って、兵たちの闊達な号令や賑やかな話し声が微かに聞こえてくる。
トゥパク・アマルは、そんな生気溢れる声を乗せて流れ来る風を全身に受けながら、今、再び、インカの民たちの到来によって命を吹き込まれ、古(いにしえ)の賑わいが舞い戻ったかのような眼下の聖都を、愛しげに見つめた。
それから、彼は、ワイナピチュの山頂に立ったまま、吹き上げる風の中で瞼を閉じる。
そして、冷風に身をあずけながら、周囲の霊験な気配に意識を集中させた。
(今も…この都は、決して死に果ててなどいない……)

トゥパク・アマルは、美しく研ぎ澄まされた目元を、ゆっくりと開く。
外見上は廃墟と化した寥々(りょうりょう)たる都ではあるのだが、目には見えねども、染み入るように清冽で力強いエネルギーが、この瞬間も、確かに、この天空都市に満ちていることを、彼は、はっきりと感じ取ることができていた。
次第に強まる風の中で、トゥパク・アマルは真っ直ぐに立ち、今一度、マチュピチュを遥々と見下ろした。
そして、静かに微笑むと、やがて、少し離れた場所に控えていたビルカパサをゆっくりと振り向いた。
「待たせてすまぬ。
そろそろ陣営に戻ろうか」
「はい、トゥパク・アマル様」
ビルカパサは俊敏に礼を払うと、サッと道を開いた。
ワイナピチュの急峻な山の斜面を敏捷な足取りで下りていくにつれ、絶壁に延々と連なる段々畑の跡地が次第に目前に迫り、ほどなく、それらの畑地に水を注ぐ水路から迸(ほどば)しる水音が、耳に心地よく響いてくる。
古の時代から、マチュピチュには、サイフォンの原理に基づく優れた灌漑技術があった。
丘陵の等高線に沿って水を引き、盛り土をしたり、逆に、削ったりしながら導水するその技術によって、ほぼ山頂に位置するこの場所でも、豊富な水を確保することができていた。

そして、たった今、この瞬間も、当時のままに水路から流れ出す清涼な水音に耳をすませながら、トゥパク・アマルが低く響く声で言う。
「ソラータでは、アンドレスが、水攻めの策を進めていると聞くが」
ビルカパサは、精悍な眼差しで頷いた。
「はい。
そのように聞いております」
ワイナピチュを下りきると、マチュピチュの一角に張った陣営に向かって二人は歩み進む。
衛兵たちが、恭しく二人に礼を払いながら、姿勢を正して素早く道を空けていく。
「アンドレスがソラータを包囲して、どれ程になるか?」
トゥパク・アマルの問いに、ビルカパサは、畏まって応える。
「はい。
間もなく、3ヶ月程になりましょう」
「そうか…。
アンドレスもよく粘ったが、さすがに、そろそろ潮時か」
「アンドレス様の策は、このまま静観ですか?」
トゥパク・アマルは、静かな横顔で頷いた。
「ソラータの街中で人質とされている民の解放が案じられるが、むこうには、あのベルムデス殿も、アパサ殿も、ついている。
下手に踏み外すことはあるまい。
それに、実際、アンドレスの水攻めの策は、あの土地であれば、あながち的をはずれてはいまい」
「はい、トゥパク・アマル様」
ビルカパサは恭順を示すと、言葉を継いだ。
「それはそうと、アンドレス様の陣営には、皇子マリアノ様もおられるはずです」
トゥパク・アマルは、再び、深く頷いた。
そして、どこか思いに耽った遠くを見やる目になって、黙って歩み進める。
決死の逃亡の果て、自分たち父母からも兄弟からも、たった一人離れて暮らす、まだ10歳の皇子を思うトゥパク・アマルの心中を思うと、さすがのビルカパサも切ない感覚に憑かれ、思わず、たたみかけるように問いかける。
「マリアノ様も、アンドレス様も、トゥパク・アマル様が牢を抜けられたことを、まだ、ご存知無いはずです。
お知らせになられたら、きっと、どれほどお喜びになられるか……!」
トゥパク・アマルは、そっと目元を細めた。
「そうだな…いずれ、近いうちに、使者をやりたいと思っている。
そして、我々も、次の段取りに向けて、早急に行動を開始したい。
アンドレスやアパサ殿が、ラ・プラタ副王領での勢力を固めている間にも、我々が、しておかねばならぬことは多い」
そう語りながら、常の沈着で美麗な眼差しに鋭さを宿して、トゥパク・アマルは、真っ直ぐ前方を見据えた。
そこに、何かの到来を、はっきりと見出しているがごとくに―――。

ビルカパサは反射的にトゥパク・アマルの視線の先を追うが、彼の視界には、長大なアンデスの霊峰が遥々と広がるのみである。
ビルカパサが、今ひとたび、トゥパク・アマルの方に向き直ると、トゥパク・アマルも、その視線をゆっくりとビルカパサの方に返した。
相変わらず沈着ながらも、強い光を宿した面差しで己を見入る主の前で、ビルカパサは、素早く居住まいを正した。
「ビルカパサ、そなたにも、そろそろ伝えておかねばならぬことがある。
この後の戦(いくさ)のことで…――」
「はっ!
何なりと!!」
ビルカパサが、逞しい体を屈め、すかさず深い恭順を払う。
トゥパク・アマルは僅かに頷くと、周囲に衛兵たちのいないことを確認し、声を落として話しはじめた。
マチュピチュの谷間を一陣の強い風がビョウと音を立てて駆け抜け、トゥパク・アマルの漆黒の長髪が、吹き抜ける風によって宙に舞い上がる。
やがて、一通りを話し終えたトゥパク・アマルの前には、愕然と身動きできずにいるビルカパサの姿があった。
「…――!!―――」

驚愕と混乱と恍惚の面持ちで、言葉を継げずにいるビルカパサに、トゥパク・アマルは、低く沈着な声で言う。
「驚かせたかもしれぬ。
無理もあるまい。
わたしとて、このことについては、かなりの思案が必要であった。
だから、ビルカパサ、そなたが納得いくまで、わたしなりの考えを幾らでも話すゆえ、何なりと問うがよい」
「――は…はい……」
普段は、トゥパク・アマルの言葉に即座の絶対的な恭順を示すビルカパサも、さすがに今は、鷲のような鋭利な横顔を強張らせ、眉間には深い皺を寄せたまま、返す言葉に詰まっている。
このビルカパサとて、単に武勇の腕に優れるのみならず、この反乱全体を常に感情統制の行き届いた冷静な視野で展望し続けてきた、慧眼の廷臣である。
そもそも、その資質なければ、トゥパク・アマルの護衛など務まるものではない。
やがて、ビルカパサは、深刻な面差しでトゥパク・アマルに幾つかの質問をした後、僅かに眉間の皺を緩めたが、しかしながら、その厳しい表情はなかなか変わらない。
トゥパク・アマルは、すっと目を伏せた。
「そなたの気持ちは分かる。
だが、既に、手はずは進めてしまっている」
「!!…――す、既に…?!
では、トゥパク・アマル様…こ…っ…このことは、皆、知っているのですか?!」
上擦った声を放つビルカパサの額には、冷風の中にもかかわらず、かなりの汗が滲んでいる。
「いや…。
まだ、このことは、ディエゴとベルムデス殿にしか伝えてはいない。
トゥンガスカの本陣戦の最中、今、そなたに話した書状を送る際に――あれは、わたしが囚われる前夜のことであったが、あの二人に内々に伝えたのみだ」
トゥパク・アマルは吹きつける風を切るようにして、雪を頂いた遥かなる霊峰に、その研ぎ澄まされた横顔を向けた。
「その後、あるいは、ベルムデス殿が遠征先のアンドレスに伝えているかもしれぬが、それも定かではない。
このようなことは、下手な伝わり方をすれば、民や兵を、いたずらに誤解と混乱の中に陥れるだけであろう。
言うまでもないが、今暫くは、そなたも決して他言はならぬ」
「は…はい……」
ビルカパサは、まだ咀嚼し切れぬ難しい面持ちで、曖昧に頷いた。
「ビルカパサ、そなたの案ずる気持ちは、よく分かる」
相手に視線を戻しながら、トゥパク・アマルが深遠な声音で続ける。

「確かに、このことに伴うリスクは、非常に大きい。
わたしの、この采配は、一歩誤れば、民を新たな苦境に追いやる危険が多大に伴うであろう。
ディエゴも、あのベルムデス殿さえ、にわかには首を縦には振らなかった。
―――だが、あれほどの火器を携えたスペイン軍主力部隊と、このまま戦闘をただ繰り返していても、遠からず、限界が来る」
「――はい……」
ビルカパサは視線を落とし、きつく唇を噛み締めた。
暫しの後、ついに、ビルカパサは吹っ切るように決然と顔を上げた。
そして、非常に真剣な眼差しでトゥパク・アマルに向き直った。
その瞳の色は、己の中に生じた多大なる惑いと懸念を踏み越えて、己の意思の元に、今、改めて、主を真っ直ぐに信じていこうという新たな強い決意に彩られている。
「トゥパク・アマル様の仰せの趣旨、良く分かりました。
その御計画が滞り無く進みますよう、わたしも最善の力を尽くしたく……!!」
「ビルカパサ…――」
トゥパク・アマルの端正な面差しが、光を宿して静かに微笑む。
一方、ビルカパサは、その太く凛々しい声音を、やや押さえながら問う。
「では、トゥパク・アマル様――その書状が先方に届いていれば…そろそろ……?」
「うむ。
何がしかの動きがある可能性はある。
早々に、極秘裏に偵察隊を放ってくれるか―――」
「はっ。
畏まりました」
「頼む」
「はっ!
ただちに!!」
めったにないほどの緊迫と恍惚を漲らせて身を低めるビルカパサの全身に、礼を払うかのように視線を走らせると、トゥパク・アマルは陣営の方へと踵を返した。

ワイナピチュの峰を背景に、いっそう強まる風に煽られながら、次第に暮れなずむマチュピチュの石畳を歩む彼の黒マントが、漆黒の翼のように大きく翻った。
ところで、トゥパク・アマルがビルカパサに語った秘密の戦略の、その展開の様相を水面下で探りはじめた頃、まだ、彼は脱獄の事実を対外的には公にしてはいなかった。
それは、スペイン側の追っ手の目を掠(かす)めるためもあったが、インカの民にとっても、戦況の不安定な現段階では混乱の元になりかねぬ危惧があったこと、及び、最も効果的な時機を捉えて民の前に現れ、一気に士気を高めたいという狙いもあってのことだった。
しかしながら、一方で、彼は、このマチュピチュを拠点として、そこから国中に通じる幾筋ものインカ道を利用し、各地に伝令を放ち、信頼できる有力な同盟者たちと密かに連絡を取りはじめた。
また、それらのインカ道を通じて国中に多くの巡視隊を放ち、戦乱による被害状況をつぶさに調べていった。
マチュピチュにはられた陣営と国中の各地とを、日々、健脚な斥候や巡視隊の密使たちが、険しい山岳の道を通って絶え間無く行き交い、トゥパク・アマルの元に様々な最新の情報をもたらした。
そして、トゥパク・アマルは、それらの情報を元に、淀みなく必要な采配を振るっていく。

今も、彼は廷臣たちと共に軍議の席に臨みながら、巡視の使者たちのもたらした情報に耳を傾け、やや沈痛な面差しで切れ長の目を伏せていた。
そして、一通り聞き終えると、全体を見渡しながら、あの低く響く声で語りはじめる。
「この反乱が幕を開けて以来、既に、1年が経とうとしている。
戦乱による爪跡は大地に痛々しく刻まれ、戦地以外の地でも、調べを進めれば進めるほど、国中の田畑の荒廃具合の甚(はなは)だしさが明らかになるばかりだ。
我がインカ軍には多くの民が義勇兵として参戦してくれているが、わたしの力不足故に、思いの外、反乱が長引いてしまった上、未だ決着を見ておらず、今、この瞬間も、国中の田畑はやむなく放置されて疲弊の一途を辿るばかり。
ましてや、戦場と化した土地の周辺は、スペイン軍の砲火に焼け焦げ、荒廃のさまは目も当てられぬ惨状……」
沈着ながらも苦渋に満ちたトゥパク・アマルの口調に、ビルカパサをはじめ――ちなみに、この頃、トゥパク・アマルの副将ディエゴは、大軍を率いて下界で守りを固めていた――その場に参集した廷臣たちも表情を重く曇らせる。
かつて農耕の合間のみを縫って戦をしていたインカ帝国時代ならば、決して有り得ぬ悲惨な現状に、トゥパク・アマルも、そして、彼の家臣たちも、非常に苦々しい思いを抱かずにはいられなかった。
さらに、トゥパク・アマルは、机上に大きく広げた地勢図の上に、しなやかな褐色の指先を走らせながら、噛み締めるように続ける。
「いや…これらの大地が荒廃しているだけではない……。
義勇兵として参戦した者たちの帰還を待ちながら、細々とながらも懸命に田畑を耕してきた女性や老人たちの苦難は、想像に余りある。
当然ながら、実際に参戦した義勇兵たちとて、この期に至っては、さすがに相当の疲労が蓄積していよう。
このまま次なる戦に臨むのは、民にとっては、あまりに負担が大きい」
廷臣たちも、その厳つい身を深く屈めて、誰しも深刻な面持ちになっている。
トゥパク・アマルは、今も静寂な眼差しのままに、そのような廷臣たちをも包み込むように全体を見渡すと、深遠な声音で決然と言う。

「今は、何も置いても、全ての民や農地の休息と救済が必要な時。
まずは、そなたたちも、そのことに意を注いでほしい。
限られた期間にできることには限界もあろうが、それでも、なお、根底から建て直す尽力無くば、我がインカの勝利なぞ、あり得まい――!!」
深く恭順を示す家臣たちの前で、トゥパク・アマルは、さらに続けていく。
「この後、義勇兵たちには報酬を与え、順次、郷里に戻して休ませる。
そして、今ひとたび、国中の同盟者たちに使者を放ち、各領内の窮状にある農民たちの救済に当たらせよ。
同盟者の多くは各地の有力な領主や豪族たちゆえ、己の領内の民や農地の状況には、あの者たちが最も精通していよう。
スペイン側の植民地支配中枢部は、今は、我らの反乱鎮圧に意識を奪われている。
各領内の細かい動きにまで目が向かぬ今なら、領主や豪族たちも、領民を庇護し救済するために、それなりに自在な采配を振るえるはずだ」
「はっ!
皇帝陛下――!!」

さらに、トゥパク・アマルは、そう遠くはない将来、再び彼が糾合をかけるその日まで、各地の同盟者たちの元で果敢に戦ってきた義勇兵たちにも報酬を与えて順次休ませ、その一方で、新たな義勇兵を募り、訓練を開始した。
また、彼自身も、クスコ近郊に陣を張る副将ディエゴを表向きの司令塔として立て、背後から己の財を投じて、疲弊した各地の農村の救済に当たりながら、戦乱による傷跡を癒すことに専心した。
実際には、それらの表向きの采配の裏側で、もう一つの重要な秘密の計略を見据えていたのだが……。
しかしながら、それについては、まだ、ほんの一握りの重側近たちしか知らぬことであった。
こうして、トゥパク・アマルは、マチュピチュを拠点に種々の指令を放ち、同盟者や同盟軍とのネットワークの強化、義勇兵の休養、その一方で新たな義勇兵の募集・訓練強化、同時に、持てる私財をも投資して国中の荒れた田畑の復興や、戦乱のしわ寄せを受けている人々の窮状の把握と援助を行いながら、反乱再起の態勢を基盤から立て直すことに尽力していった。
次なる反乱の展開のために…――!
そう…次こそ、真に、この反乱の最終決戦になるであろう、その日のために―――!!
こうして、ペルー副王領にて、トゥパク・アマルが、反乱再起に向けて基盤を根底から立て直そうとしている頃、隣国ラ・プラタ副王領のアンドレスも、また、ソラータ奪還を賭けて果敢に行動を続けていた。
かくして、アンドレスの呼びかけに応じて陣営に馳せ参じた多数の民たちの協力のおかげで、彼が推し進めていた「水攻め」作戦に向けた河川の土木工事は、急速なピッチで進み続けた。
そして、多くの協力者を得て、当初の予想を超える速さで、ついに川は堰き止められ、敵の立て篭もるソラータの市街と川とを結ぶ長大な堤防が完成した。

その日、茜色に染まる夕刻時の空の下、自軍の兵や参集した民たちに見守られながら、アンドレスは凛として川岸に立っていた。
彼の眼前に広がる長大な堤防は、その壮観さを見せつけるがごとくの気迫で、堂々たる勇姿を目に焼き付けてくる。
アンドレスは、そして、彼のみならず、そこにいる誰もが、激しく感無量の思いを噛み締めていた。
「アンドレス様、これを……」
傍に控えていたインカ兵が、恭しい手つきで捧げ持つようにして、アンドレスに、黄金の杯を差し出した。
「ありがとう」
我に返ったアンドレスは、その儀式用の特別の杯を、丁寧に両手で受け取る。
兵は、アンドレスに手渡した杯に、乳白色の滑らかな液体――インカ古来からの伝統的なトウモロコシの酒、チチャ――を注いでいく。
今、工事完成の感謝を捧げ、策の成功を祈って、神々への儀式を執り行うアンドレスを遠巻きにするようにして、かなりの兵や民衆が集まっているにもかかわらず、まるで酒を注ぐ微かな音さえ聞こえるほどに、辺りは厳粛な気配に静まり返っている。
やがて、注ぎ終えた兵が素早く下がると、アンドレスは、背後の大群衆を振り返り、杯を掲げて深く礼を払った。
(ありがとう…!!
皆の協力が無ければ、決して、短期間での、これほどの大規模な工事の完成などありえなかった。
本当にありがとう…――!!)
他方、兵や民も、輝く瞳を伏せて、深々と礼を払い返す。
そして、それらの人々の間から、そっとアンドレスの姿を見守るコイユールも、また、遥々と展開する壮大な堤防を前にして、深い感動を噛み締めていた。
(まさか…あの夜の、ほんの水遊びが、これほどのことになるなんて……!
―――なんだか、夢を見ているよう……)
思わず零れた涙を細い指先で拭うと、コイユールは本当に夢見心地で、遥か離れた場所から、衆目の中に凛然と立つアンドレスの姿を見つめていた。
一方、コイユールのずっと先の川岸では、巨大な堤防の広がる川の方へと再び向き直ったアンドレスが、天空の神々にチチャ酒を捧げるようにして、空に高々と黄金の杯を掲げている。
それから、大地の神へ…そして、川の神へと――彼が杯を動かすたび、西日を受けて、杯が黄金色の眩い閃光を放つ。

儀式用の深紫色の衣装に、インカ皇族たちの纏う黒マントをゆるやかに肩から回し、夕風を受けて真っ直ぐに岸辺に立つアンドレスからは、若々しく清冽な雰囲気が芳しく放たれている。
周囲の兵や民たちが息詰めて見入る視線の先で、彼は掲げ上げた杯を僅かに傾け、大地と川にチチャ酒を注いだ。
乳白色の液体が、地中に、そして、水中に、溶けるように吸い込まれていく。
やがて、チチャ酒を神々に捧げ終わると、アンドレスは、今ひとたび、神々に礼を払うかのように目を伏せた。
それから、黄金の杯に、己自身も唇を触れる。
アンドレスが杯を飲み干すと周囲の兵や民から和やかな喝采が上がり、それが合図であったかのように、その場に参集していた人々にも、僅かずつながらも酒が振舞われていく。
その場の雰囲気は、厳粛な儀式の場のそれから、たちまち、ささやかな宴の場のそれへと移っていった。
互いの労を賑やかにねぎらい合う群集の様子を、暫しの間、眩しそうに眺め入った後、アンドレスは、改めて、完成したばかりの堤防へと視線を返した。
彫像のように研ぎ澄まされた横顔に、強い恍惚と鋭気が漲る。
(いよいよだ…!!
いよいよ、明朝……水攻めを決行する――!!)
ついに決行を目前にしたアンドレスの全身を、ゾクゾクと武者震いが走った。
だが、次の瞬間には、急激に不安に突き上げられる。
(明日の作戦は、単に、ソラータの街を大水で襲い、敵を潰せばいいのではない……!
同時に、ソラータの住民たちを救出しなければならないのだ。
策は練ってある…――だけど、本当に上手くいくだろうか……?)
堤防を睨み据えるほどに、いつしか非常に険しい表情になっているアンドレスの脇に、老練の重臣ベルムデスがそっと近づいた。
「アンドレス様、いよいよ決行は明朝ですな」
「はい…!!
今度こそ、何としても成功させねばなりません……!!」
きつく唇を噛み締めるアンドレスを温厚な眼差しで見つめた後、やや目を伏せて、ベルムデスは手元のチチャ酒に口をつけた。
「アンドレス様、大分お力が入っておられるご様子。
これは、まだ酒が足りませぬな?」
「え…?!
あ……」
目元に皺を寄せながら、にこやかに語るベルムデスの脇で、アンドレスはハッと己の手元に視線を落とした。
無意識のうちに、指の爪が手の平に喰い込むほどに、激しく拳を握り締めていたのだ。
彼は血の滲みかけた手の平を慌てて開いて、サッと後ろ手に回した。
そんなアンドレスに静かに微笑みながら、ベルムデスは眩い西日を放つ地平線へと横顔を向ける。
「ご覧くださいませ。
インカの神々も、あなた様の捧げた酒に酔いしれておられる。
明日は、必ずや、あなた様をご加護くださいましょうぞ」
温和でありながらも深遠なベルムデスの声音につられるように、アンドレスも、そちらを眺めやった。

確かに、いつにも増して煌々たる黄金色の輝きを放ちながら、光の筋を描くように地平線上を染め上げる巨大な太陽の姿は、真に神々が大いなる加護の手を広げ、導いているようにさえ見える。
アンドレスは黄金の杯を手にしたまま、吸い込まれるように夕陽に見入った。
他方、アンドレスの背後から、今度は、朋友ロレンソの声が響いた。
「アンドレス!!」
ハッと振り向いたアンドレスの目に、常の勇壮な戦士の衣装から、今は、すっかり平民の服装へと扮した友の姿が映る。
「あ……」
「アンドレス、こちらの準備は整った!
そろそろソラータの市街地に向かう」
そう言いながら俊敏な足取りで近づいてくる友の姿に、アンドレスは、しげしげと見入った。
策のために、平民に扮したロレンソは、簡素な麻布のシャツに色褪せた農作業用のズボン、その上に擦り切れた皮製のポンチョを被るように着込んでいる。
「どうだ?
なかなか似合うであろう?」
笑顔で問うロレンソに、しかし、生粋の貴族で、戦士の中でも特に精悍で鋭利な風貌と雰囲気を持つ彼には、平民の扮装は、どこか違和感を拭えない。
「はは…まぁ……な…」
苦笑しながら、そんな曖昧な返事をするアンドレスに、ロレンソは斜めに睨んで詰め寄った。
「なんだ、アンドレス?
そなたの案ゆえ、わたしはこれでも、かなり気合を入れて変装したのだが…?」

「いや、すまない…悪くないぞ!
ソラータの若い娘たちが、すっかり釘付けられそうだ」
アンドレスは半ば茶化し、半ば宥(なだ)めるように、朋友の逞しい肩に腕を回しながら笑顔で陣営の方へと歩み出す。
「それで、ロレンソ、君と共にソラータの市街地に入ってもらう他の兵たちも、準備はできているか?」
「ああ、万全だ。
日が落ちたら、今夜中にソラータの街中に潜入する」
連れ立って陣営に向かって歩み進めながら、アンドレスは引き締まった横顔で頷いた。
「君が行ってくれれば心強い。
だが、くれぐれも、ギリギリまで敵兵に勘付かれないよう気をつけてくれよ」
「そなたに言われるまでもない。
ソラータの住民たちのことは、我々に任せておけ」
そう言って頼もしい笑顔を見せるロレンソの肩に回した腕に力を込めながら、アンドレスも微笑んだ。
「ありがとう、ロレンソ」

そして、己自身にも言い聞かせるがごとくに、噛み締めるように言う。
「あとは……こっちに残る俺たちが、必ず上手くやる――…!」
「ああ。
頼んだぞ、アンドレス。
わたしたちまで、水底に沈めないでくれよ!」
ロレンソは凛々しい面差しで、もう一度、微笑むと、「では、行って参る!」と、アンドレスの腕をほどいた。
先程までの煌々たる太陽が地平線に姿を消すと、たちまち夜の帳がおりてくる。
さっと踵を返して颯爽と立ち去る友の勇姿を見送ると、アンドレスも、鋭い眼差しで陣営へと急いだ。
こうして、翌朝の決行に向けて、アンドレスが最終的な打ち合わせの軍議を開いていた頃、ソラータの市街地の水は既に濁りはじめており、ソラータに立て篭もる敵軍は、激しい警戒を強めていた。
当地のスペイン軍側の指揮を執るピネーロは、インカ軍陣営傍の河川まで偵察に行かせた斥候たちの報告に、非常に険しい表情になっていく。
そもそも、あれほどの大規模な工事を行なうインカ軍の動きに、いくら市街地に立て篭もっているとはいえ、ソラータのスペイン軍が、何も勘付かずにいるはずなどなかった。

かつて、未遂とはいえアンドレス暗殺の実行犯をも務め、さらには、己の上官たるスワレス大佐の身柄がインカ軍に捕縛されても、なお、微動だにしなかった、冷徹で強硬な「籠城派」のピネーロ――だが、さすがに此度ばかりは、彼も危機感を募らせていた。
アンデス山岳地帯の中でも特に高所の多いラ・プラタ副王領(註:現在のボリビア界隈)では、その薄い空気に適応して生きるために、必然的に、人の住む集落は、周囲の自然に対して、盆地や窪地などの低地に築かれている場合が多い。
そうすることによって、人々は、少しでも多くの酸素を得ようとしていたのである。
このソラータとて類に漏れず、従って、市街地に高所から水を大量に流し込まれれば、非常に不味いことになるのは明白だった。
ピネーロは、既に、数日前には、このラ・プラタ副王領における反乱軍討伐隊の総指揮官フロレス――現在は、トゥパク・アマルの最も有力な同盟軍たるアパサ軍と、ラ・パスにて激闘を展開中である――の元に、援軍要請の使者を放っていた。
しかしながら、当のフロレス軍自体が、あの暴れ者で豪腕な猛将アパサに酷く手を焼かされており、援軍を送ることに手間取っていたこと、及び、アンドレス軍の予想を超える速さの工事の進捗のために、もはや、ピネーロは、水攻め決行までに援軍到着の可能性は低かろうと悟りはじめていた。
(―――アンドレス…あの若造め……!)
ソラータのスペイン軍陣営で軍議の席に臨みながら、黒々とした顎鬚に覆われたピネーロの面持ちが、苛立たしげに歪む。
ギリギリと切歯扼腕しながら、ピネーロは部下たちを、いっそう険しい目で睨み据えた。
「市街地の住民たちに、妙な動きは無いか?」
やはり非常に難しい表情の部下たちが、畏まって応える。
「はい…――。
現在のところは、変わった動きは見られませんが…」
ピネーロは中年の貫禄を漲らせた厳(いか)つい肩をいからせながら、先刻から、しきりに苛々と顎鬚をさすっている。
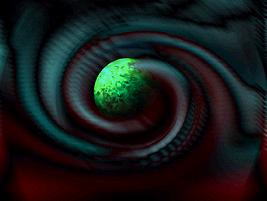
やがて、低い、冷徹な声で、地を這うように言う。
「あのアンドレスのことだ……。
我が軍を完全包囲までしておきながら、飢え苦しむ住民を見捨てられず、結果、我が軍の補給路を完全に断つことを最後までしなかった。
そのアンドレスが、インカ族の住民たちまで水攻めに巻き込むことなど、絶対に、あり得まい。
水攻めを実行する前に、必ず、住民たちを逃がそうとするはずだ。
なれば、我らは、住民たちを逃さぬことが肝要。
即刻、ソラータの住民たちの見張りに回す人員を倍加し、夜を徹して監視を強めろ。
よいな。
絶対に、逃がすな―――」
「はっ!!」
激しい緊迫感を滲ませた彫りの深い横顔で、白人兵たちの冷酷な眼光が、一際、強く放たれた。
しかし、その頃には、ソラータの市街地を囲む裏山の一角に、ロレンソ率いる凡そ千人程の精鋭のインカ兵たちが、平民に扮した姿で、息詰めて潜伏していた。
高地の冬の外気の冷たさは尋常ではないが、この反乱期を通じて野晒しの生活や戦闘にも慣れている兵たちは、支給されたコカの葉を噛みながら、深い闇の中で、獲物を狙う獣のように完全に気配を消している。

そして、連隊長たるロレンソ自身は、数名のインカ兵たちと共に山を下り、既に市街地の中まで潜入していた。
時は、間もなく、深夜12時を回ろうとしている―――。
「あれが、ソラータの住人たちの長(おさ)の家か?」
闇の中で、低く声を落として問うロレンソに、「はい。事前の調べで、間違いございません」と、部下が小声で早口に応える。
市街地の一角で、彼らは草陰に身を隠したまま、辺りの様子に神経を集中させた。
深夜にもかかわらず、スペイン兵たちが街中を執拗に徘徊しながら、住民の動向に監視の目を厳重に光らせている。
「くそ…!
予想以上に、監視のスペイン兵が多いですね、ロレンソ様」
ひそひそ声で囁く部下に、ロレンソは、鋭利な横顔で頷いた。
「ああ。
この様子では、水攻めが近いことを完全に気付かれているな……。
そなたたちも、決して、我らが兵士であることを悟られるなよ」
周囲の兵たちが、気配で敏捷に頷き返す。
やがて、見張りのスペイン兵たちの往来が途切れた時機を見計らって、ロレンソは、俊敏に草むらから家の方へと踏み出した。
心配そうに、草陰の中で兵たちが身を乗り出す。
「ロレンソ様!
お一人で…?!」
「複数では目立つ。
見張りを頼む――」
ロレンソは早口で低く応えると、気配を消したまま、たちまち長の家の方へと走り去った。
簡素な石造りの家の前まで来ると、窓辺から、ランプの光が僅かに漏れている。
ロレンソは壁に身を寄せ、中の気配に意識を集中させた。
(家の中に、何人か集まっている…?
何か話し合いでもしているか?
それもそうか――深夜とはいえ、これ程に物々しくスペイン兵たちの監視が強まっては、さすがに、ただ事ではなかろうと察してもいよう……)
ロレンソは、敏捷に窓の下に回り込むと、今度は周囲の気配に神経を張り巡らせながら、窓を慎重にノックした。
室内からハッと息詰める気配があり、強い緊迫感の走るのが伝わってくる。
暫しの間があった後、やがて高齢のインカ族の男が、警戒の面持ちで窓辺に顔の一部を覗かせた。
骨ばった痩せた体格に、深い皺の刻まれた褐色の顔は白い鬚で覆われ、その中で窪んだ目が静かに光っている。
ひどく重々しい労苦を背負った気配と、それでいて、どこか研ぎ澄まされた厳然とした雰囲気に、この老人が長か――と、ロレンソは素早く直観した。
窓を隔てた向こうから、ロレンソは眼差しで深く礼を払う。
「わたしは、アンドレス様の軍から遣わされたインカ軍の兵士。
貴殿に大事なお話が……!」
一方、長と思われる窓辺の老人は、唐突な来訪者を驚きと警戒の目で見つめている。
ロレンソは、さらに畳み掛けた。
「時間がありません。
わたしを中に入れてください!」

真剣な表情で決然と口を動かしている窓外の若者は、それこそ貧しい平民の服装を纏ってはいるが、その高貴で鋭利な風貌と、いかにも戦士らしい精悍で逞しい体躯、そして、隙の無い振る舞いは、素人目にも一介の平民には見えない。
増してや、長らしい慧眼をも備えたこの老人には、若者の言葉を信じるのに、そう時間はかからなかった。
長は、屋外にスペイン兵たちの気配が途切れていることを確認すると、ロレンソを家に招き入れるため、足早に戸口に向かった。
窓辺の老人が戸口の方へと消えた様子から、ロレンソも、闇に紛れながら扉の方へと走る。
道を隔てた草陰からロレンソの動きを見守っていたインカ兵たちは、「よし!ひとまず、長との話はできそうだぞ」と、互いに目配せした。
そんな部下たちの眼差しが注がれる中、間もなく、ロレンソは長の家の中へと姿を消していった。
一般庶民たちのアドベ(日干しレンガ)造りの家に比して、この建造物は、インカの伝統的な精緻な石組みが特徴的で、確かに、長の家らしい堅固な構えではある。
だが、それにしては、家の中は質素を通り越して、あまりに閑散たる萎びた状態であった。
これほどの寒さの中、当然のように、まともな火の気すら無い。
老人の後について、冷え冷えとした薄暗い廊下を進みながら、チラッと垣間見えた台所界隈には、僅かな食物の欠片さえ、ありそうな気配は無かった。
(アンドレスがこの街を完全包囲して以来、立て篭もる敵軍と膠着する中、住民は完全に食糧が尽き、惨憺たる状態だったと聞く。
民は、ラバや犬、猫、鼠ばかりか、靴の踵(かかと)まで食べていたと…!
その後、アンドレスが幾らかの物資の補給を続けてきたとはいえ、結局は、おおかた敵兵たちに奪われてしまっていたのは明白だ……)

ロレンソは唇を噛み締め、鋭利な目元をそびやかせた。
(この街の住民たちは、もう何ヶ月も、このような状態に置かれてきたのだ。
常に、敵兵に見張ら続け、いつ命を落とすかも分からぬ戦々恐々たる状況下で逃れる術も無く、最低限の食料も無くでは…――まともな神経ではいられまい。
いくら敵が立て篭もっているからとはいえ、何の罪も無い民に、このような酷い状態を強いてきた我々インカ軍の責は、重すぎる……!)
すっかり険しい表情になったロレンソが通された居間では、油の切れそうな薄暗いランプの元、5〜6名のインカ族の男たちが、緊張した面持ちで待っていた。
ロレンソは、その場にいる男たちの様子を俊敏に観察する。
年齢低には40〜50歳前後と見受けられたが、恐らく、栄養不良のためであろう、酷くやつれており、年齢以上に見えているのかもしれない。
皆、痩せ細り、すっかり疲れ切った表情である。
が、それでも、なお、どこか鋭く、頑とした力強さを残した眼光から、長と共に街を治める立場にある者たちではなかろうかと推測できた。
他方、男たちは、自分たちよりもずっと年若いにもかかわらず、非常に凛然とした雰囲気と強い存在感を放つロレンソの姿に、観察するというよりも、むしろ、すっかり見入ってしまっている。
ロレンソは、長と男たちに丁寧に礼を払った。
「このような突然の訪問、驚かせて、かたじけなく思います。
わたしは、このソラータを包囲しているアンドレス軍の兵、ロレンソと申す者。
どうしても急ぎお伝えせねばならぬことがあり、参りました」
彼がちらりと視線を走らせた先で、老人は、深々と身を屈めて礼を払うと、ゆっくりと顔を上げた。
そして、低く、しわがれた声で、はじめて口を開く。
「ロレンソ様、このような所まで、よくぞお越しくだされました。
わたしが、このソラータの長(おさ)でございます。
いや…長とはいえ、それは名ばかりで、今のわたしには何の力もありませんが……。
あの白い西洋人どもが、すっかり、この街を牛耳っておりますからな」
ロレンソの表情に沈痛な色が走るのを長は素早く見て取ると、急いで言葉を継いだ。
「いやいや、ロレンソ様、どうかお気を悪くされないでくださいませ。
このソラータの民は、皆、アンドレス様の軍がお助けくださると信じ続けております。
本当に、あなた様方だけが、頼りなのでございます」
そう言いながら、老人は周囲の男たちを見渡した。
「ご安心くださいませ。
ここにいる者は皆、信頼できる者たちです。
さあ、どうか、ロレンソ様、お座りを……」
中央へと着座を促され、ロレンソは男たちの輪に近づいた。
いかに平民に扮していようとも、今、この場では、ロレンソは、本来の己の持つ気配を隠す必要は感じていなかった。
むしろ、本来の己の持ち味を生かして、ここにいる者たちの士気を高めることこそ重要なのだ――。
「では…」
ロレンソが同じテーブルを囲んで席に着くと、男たちの間から、低く溜息が漏れた。

痩せ細った男たちの中で、鍛えられた精悍で逞しい体躯のロレンソは、同じインカ族とは思えぬほど際立っている。
しかも、ランプの明かりを受けて、闇の中に浮き立つ彼の匂い立つような高貴で凛々しい風貌には、長も男たちも、思わず釘付けられずにはいられない。
同時に、今まで「人質」として身を縮めるばかりだった己たちもが、今は、インカのために何事かを為し得る同志となったかのような、不思議な恍惚と沸き立つ何かに、にわかに激しく突き上げられた。
いつしか、その場の誰もが、やや前傾姿勢になって身を乗り出している。
ロレンソは、そのような男たちの様子と場の空気の高まりを、隙無く冷静に読み取りながら、低く、沈着な声で語りはじめる。
「この街のすぐ傍には、既に、住民たちを守るための凡そ千人のインカ兵が、平民に扮して控えています。
我々は、このソラータの民全員を、安全に助け出すために参りました」
そこまで言うと、ロレンソは、やや苦しげな眼差しで一呼吸置き、再び、続けていく。
「我がインカ軍が、これまで、このソラータのそなたたちに蒙らせて参った苦難は、どれほど償おうとも償い切れぬほどのもの。
もはや、これ以上の犠牲や苦境は、誰一人においても、続いてはなりません。
このような悲惨な状況は、今宵限りで、完全に終わらせねばなりますまい。
そのために、そなたたち皆の協力が必要なのです……!」
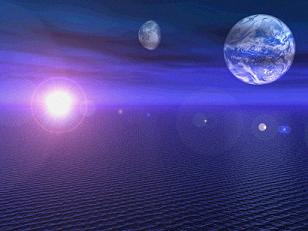
ランプの芯が燃える音と共に、その光がにわかに強まる。
光を受ける長と男たちの横顔に、いっそう強い緊張と恍惚が走った。
ロレンソは鋭利な目元を細め、より低く、真摯に、噛み含めるように続ける。
「どうか落ち着いて聞いてください。
そして、わたしの言う通りに行動してください。
明朝……このソラータは、アンドレス軍によって、水攻めを受ける―――」
「!!!」
一方、それから暫しの後の敵陣―――。
ソラータの街中に立て篭もるスペイン軍の陣営では、深夜にもかかわらず、真昼のごとくの騒然たる様相が続いていた。
河川傍のアンドレス陣営と、街中とに、次々と偵察の斥候を放っては、その報告を受ける敵将ピネーロは、あの頑とした険しい形相をいっそう険しくさせて、苛々と顎鬚をさすり続けている。
既に、時は、深夜3時を回ろうとしている。
だが、今だに、住民たちに特別な動きは見られない。
夜を徹して、住民たちを逃さぬための厳重な監視体勢を続けているが、一人とて、街から逃げ出した様子はなかった。
街は、いつも通り、疲れ切った翼を投げ出すかのようにして、ただ、夜のまどろみの中にいる。
ピネーロは、深く眉間に皺を寄せた。
(アンドレス…何故、住民たちを逃がそうとしない…?
水攻めは、すぐには行わない算段か?
だが、あの工事の完成具合にしろ、あの界隈のインカ兵どもの動きにしろ、明らかに、作戦決行前夜の体勢ではないか……!!)
奥歯をギリギリ鳴らしながらも、ピネーロの額には、ブツブツと無数の脂汗が滲んでいる。
火の粉を巻き上げる松明の火が汗粒に反射して、額が不気味に照りかえる。
(まさか――此度に至っては、あのアンドレスも、ついに住民を見捨てる気になったのか?)
ピネーロは、分厚い胸板を反らしながら、手の甲で乱暴に脂汗を拭った。
(いや、それは有り得ぬ!!
何事にも甘いあの若造は、今までも、幾度と無く、好機を自ら台無しにしてきたではないか。
此度とて、住民を見捨てることなどできはすまい。
必ず、助け出そうとするはずだ。
だが…ならば、何故、何も動きをみせぬ…?
若造…何を考えている……?)
どす黒いオーラを放ちながら、大股で陣営を歩み進むピネーロの傍に、インカ軍の偵察へと参じてきたばかりの斥候が走り寄り、その足元に跪いた。
ピネーロは、ギッとした黄色い眼光で斥候を見据えた。
「インカ軍の様子は?」
「はっ!
畏れながら…」
斥候は息を切らしながら、青ざめた顔で唇を噛む。
「インカ軍の陣営では、既に、無数の兵たちが河川に結集し、今にも水攻めを決行せんとの体勢に入っております!!」
ピネーロは、骨の砕けるほどに拳を握り締めた。
赤黒い松明の炎が、メラメラと夜空に燃え上がった。
彼の傍に控えていた副官が、やはり非常に険しい表情のまま、低く問う。
「ピネーロ様、いかがいたしましょう?
このまま水攻めに踏み切られては、我が軍の犠牲も、甚大なるものに……」
「くそっ……!
そんなことは、言われずとも、分かっておる!!」
吐き捨てるように言うと、ピネーロは、副官を鬼のような形相で睨み据えた。
とはいえ、いかに感情が煮えくり返っていようが、さすがにピネーロも大軍の将である。
冷静さを容易く完全には失わない。
ピネーロは、副官に向き直った。

「住民どもの監視を引き続き続けよ。
…が、我が軍を撤退する準備も同時に進めておけ。
――だが、間違っても、まだ動くなよ。
向こうも、住民を助ける素振りを敢えて見せず、我々を混乱させようとしているのかもしれぬ。
あるいは、我が軍が退却する気配を見せる隙を突いて、住民どもを逃そうとの算段かもしれぬ。
あのアンドレスのことは、読めている。
あの者が如何に装おうとも、最終的には、絶対に、住民を犠牲にすることなどできぬ。
住民を街に残したまま、水攻めなど…――!!」
そう己にも言い聞かせるかのように、断固たる口調でピネーロが言い放つ。
が、その内心では、ピネーロ自身、己への確信が少しずつ揺らぎはじめているのを感じていた。
無意識のうちに己の顎鬚を荒々しく掻き毟りながら見上げる夜空は、微光を帯びて、既に僅かな白みを帯びていた―――。
その頃、インカ軍の陣営では、作戦決行の準備を万端に整え、長大な堤防の各所に整然と布陣した兵たちを、高台から見守るアンドレスの姿があった。
夜明け近い冬の冷風を全身に受けながら、彼は、各持ち場にて、最終的な作業の段取りを詰めている約2万の兵たちを遥々と見渡した。
決行の時は、確実に近づいている―――!!
落ち着こうにも、高鳴り、逸(はや)りそうになる胸を、思わず、押さえる。
そんな彼の元には、ロレンソ一行との連絡のために往復する兵たちや、立て篭もるスペイン軍の様子を探りに行き来する斥候たちが、絶え間なく参じては、つぶさに状況を報告していく。
そして、今も、敵情を視察して戻ったばかりの兵が、アンドレスの傍に勢い良く走り込んできた。
「アンドレス様、敵は、いよいよ、退却の準備をはじめたもようです!!」
「そうか!!」
アンドレスは、大きく顔を輝かせて身を乗り出した。
「それで、敵は、動きそうなのか?!」
偵察の兵は、身を屈めてアンドレスを見上げながら、僅かに首を振った。
「いえ…まだ、実際には、動く気配はありません。
向こうもこちらの様子を、逐一、探っております。
あの敵将ピネーロは、アンドレス様が住民を見捨てるはずはあるまいと、今も頑として思っているようです。
敵軍は、アンドレス様が住民を助けぬ素振りを装って、彼らを混乱させようとの算段ではないかとまで勘繰っております。
如何に装おうとも、アンドレス様が住民たちを見捨てるはずはあるまいと…―――」
「そうか……」
アンドレスは、やや俯(うつむ)いて苦笑しつつも、「あのピネーロに、俺のことを見切られているのは分かっているさ」と、半ば開き直った調子で呟いた。
それから、彼は兵に向き、丁寧に礼を払う。
「ありがとう。
引き続き、敵の動きを見張ってくれ」
「はっ!!」

兵が闊達に返事をして下がると、アンドレスは、「よし…!」と、誰にとも無く呟いて、抜けるような群青色の空を振り仰いだ。
夜空では、既に、明けの明星が、白い清らかな光を放っていた。
かくして、明けの明星が瞬く夜明け近い空の下、ソラータの住民たちを助けるために派遣されたロレンソ軍も、計画の駒を着実に進めつつあった。
今、彼らは、敵兵の目を掠(かす)めるために、街を囲む裏山の獣道を敏捷に移動しながら、街傍の各所に散って配置についていた。
かなり地平線に傾きかけた月明りを頼りに、ロレンソは各部隊を纏める隊長たちと共に、ソラータの綿密な地図を囲んで最終的な打ち合わせを詰めていた。
兵たちの中には、先刻の長との話し合いに加わっていた街のインカ族の男たちも、混ざっている。
彼らが囲む地図上では、街を5〜6個のブロックに分けた線が朱色で示されていた。
ロレンソは、それらの各ブロックを褐色の指先でなぞりながら、集まった兵や男たちに、最終確認をするように、低めた声で念を押す。
「打ち合わせ通り、住民たちの救出は、ここに示した各ブロックごとだ。
各ブロックからの非難ルートを、各自、もう一度、よく確認しておいてくれ」

彼はゆっくりと顔を上げ、ソラータの男たちの方へ眼差しで礼を払った。
それから、再び、兵たちに視線を戻す。
「ここに参加してくれている彼らは、長の家で出会った方々だ。
街の住民でもあり、街の各ブロックを取り纏めている者たちでもある。
それ故、住民たちのことにも、地理的なことにも、明るい。
これから、共に、協働して事を進めていく」
インカ兵たちが、精悍な横顔で、礼を払うように男たちに頷いた。
一方、ソラータの男たちの横顔にも、強い緊迫と恍惚が走る。
ソラータの痩せた男たちの瞳に、今、再び闘志が燃え上がるのを見て取りながらも、ロレンソの鋭い観察眼は、彼らの中に残る強い不安の気配をも決して見過ごさない。
ロレンソは、沈着な声音で、続けた。
「ご案じあるな。
敵に目立たぬよう、今は兵士の身なりはしていないが、我々は、しかと武器も身に備えております。
いざとなれば、我々が敵兵の盾となり、そなたたちや街の住民たちをお守りいたします」
「で、では…ソラータの街中で、戦になるかもしれないのですか…?!
しかし、敵は数万はおります!
ここにいるあなたたちの人数では……!!」
ソラータの男の一人が青ざめて、縋(すが)るような視線を向ける。
ロレンソは、僅かに目を伏せて、静かに頷いた。
「確かに、この状況でなくば、ここにいる千の兵だけでは、あまりに心もとない。
が、此度は状況が違う。
増してや、此度の策の実行には、堤防での作業に大掛かりな人数を要するのです。
そして、その作業こそが、此度の策の成否を左右する」

含みをもたせたロレンソの言葉に、その場にいた他のインカ兵たちも、鋭気を漲らせた精悍な面持ちで、力強く頷いている。
ロレンソは、今ひとたび、ソラータの男たちそれぞれに、礼を払うように凛々しい眼差しを向けてから、低く、決然と続けた。
「ご案じあるな。
我らと共に、大水が、そなたたちを守ってくれましょう―――!」
こうして、ついに――作戦決行の時が迫る。
日が昇り出して間もない朝焼けの中、川岸の堤防周辺に結集した約2万のインカ兵たちは、最前線に立つがごとくの強い緊張感と、いよいよ時を迎えた興奮と鋭気とに満ちた表情で、各自の持ち場についていた。
そして、一際小高い丘の上には、決然と立つ全軍の総指揮官アンドレスの姿―――。
普段の柔らかな風貌も、今は張り詰めた緊迫感と鋭利な気配とを増し、光で射るような眼差しは、隙無く、眼前で堰き止められた川と堤防に向けられている。
合図を待つ兵たちの真剣な視線を一心に受け留めながら、彼は両足で大地を踏みしめ、体の中心部まで奥深く息を吸い込んだ。
引き締まった右腕を、その腰に提げた剣へと移動していく。
柄を握り締めた瞬間、電撃が手の平から腕に走るような強い衝撃を感じ、暫し眠りについていた剣が脈動をはじめるのが分かる。
アンドレスは柄を握る指先に力を込めると、その重厚な剣を、スラリと鞘から抜いた。
鋼色の刃に、蒼い覇光が走る。
そのまま、ゆっくりと、彼は右腕を宙高く振り上げた。
鋭く滑らかな剣先が、陽光を受けて黄金色の閃光を放つ。

さらに昇りゆく陽光を反射し、煌々と燃えるような輝きを増す剣先は、まるで、そこに太陽神が宿ったかのようにさえ見える。
全軍の兵が息を詰め、その輝きの前に、心が、魂が、完全に一つに合わさっていく瞬間――!
アンドレスは、眼下の全軍を鋭い視線で見渡すと、決然と剣を振り下ろした。
いざや、決行―――!!!


